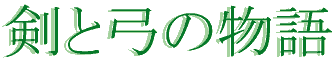
--東洋編2<日本>--

|
| [TOP] | [EAST1] | [WEST1] |
☆私lv1uniが主体で書いた項目は◇、幻夢の天魁星さんが主体で書かれた項目は◆がついています。
☆日本の「太刀」について
幻夢の天魁星よりいただきました、 非常に詳しい内容です。幻想水滸伝のゲオルク様の武器であられます太刀は、 気のせいかもしれませんが、ひいきされているようです(私もですけど^^;)。 では、太刀の全てをどうぞ。
1.形状と用法
太刀は刀身の長さが2尺(約60cm)以上の、大きく反りをつけた彎刀(わんとう)で す。造込みは鎬造(しのぎづくり)で、茎形式。茎には鮫革や樺を巻いた木製の把がはめら れ、練革か鉄あるいは金銅製の鍔(つば)がつけられています。
実用的な太刀は、刀身長75cm前後のものが一般的です。把をつけて全長90〜100c mくらいが、騎馬でも地上の戦闘でも最も扱いやすかったのです。他にも長短の刀身がありま すが、2尺(約60cm)以下のごく短いものは「小太刀」、3尺(約90cm)以上の長大 なものは「大太刀」と呼んで区別されます。
刀身の長さだけでいえば、打刀もほとんど同じなのですが、その区別は着用法の違いにあり ます。太刀は鞘に設けた足金物(あしがなもの)に帯取の緒をつけ、刃を下に向けて腰に吊る します。これを「佩く」(はく)と言います。それに対して、打刀は刃を上にして腰に差すと いう違いがあります。同じ日本刀ですから造込みも大差なく、長さも同じだとしたら、ではど こで刀身の区別ができるかということになります。 その決め手は刀工の銘を刻む位置です。太刀は棟を上に向けて佩きますから、腰に吊るす時 に外側になる佩表(はきおもて)の刀面に作銘を刻むのが通例です。逆に打刀は太刀と反対の 面に銘が入ります。ですから外装(鞘に金足物がついている)を見なくても太刀と識別するこ とが可能なわけです。
太刀は基本的に両手で握って扱う時には、斬攻力が非常に高くなり、腕を斬り落とすくらい の威力があります。また、騎乗では片手で扱いますが、刀身が大きく反っていますから、馬上 から斬りつけるにも適しています。とにかく斬る性能に優れ、比較的軽量であるため扱いやす く、攻撃にも防御にも便利であるというのが太刀の利点です。もちろんこうした特色は日本刀 全体に言えることです。 逆に、太刀の欠点は着用の仕方にあります。腰にぶら下げていますから、馬上では良いとし ても地上での素早い移動には邪魔になります。それが後に打刀の様式に取って代わられる要因 でもあります。
直刀の場合は、突くことが中心でしたから操作技術としては、比較的単純なものでしたが、 太刀が登場すると「斬る」「突く」「払う」あるいは「投げる」ことも含めて、その操作技術 は複雑になります。とはいっても太刀が使われた鎌倉、南北朝時代は、まだまだ力にまかせて 斬りつけるという用法が主で、いわゆる「剣術」といものが本格的に発達するのは、室町時代 以降のことです。
2.歴史と詳細
ちょっとくどくなりますが、平安時代初期まで流行した直刀は、突くのには適しているが、 斬るのにはあまり便利な兵器ではありませんでした。そこで、刀身に反りをつけ、それととも に造込みも直刀の平造または切刃造よりも強固な形式である鎬造り(しのぎづくり)という鍛 造方法を考案し、武器としての能力を高めたのです。極論すればこれは日本の武器の大きな 「革命」でした。つまり、刀剣は古代から江戸時代まで常に主力武器でした。その中で奈良時 代までの刀剣は、外来の文化をそのまま利用した直刀だったのに対し、完全に日本固有のもの へといわば自立したのです。
では何故日本刀という世界的にも独特な刀剣の形式が生まれたのか。それについては色々論 じられていますが、結論らしきものとしては、中国にも西洋にもないということは、日本人の 民族的風土的感性、美意識といったものが大きな要因としてあるのではないかということで す。
もちろん武器が進歩、発展する具体的要因は別にあります。彎刀が登場する時代背景には、 源氏と平家を棟梁とする武家の台頭がまず上げられます。武士の登場は、それまでの徒歩戦か ら騎馬戦へと戦闘形態を変化させ、馬上戦での武器の威力、操作の便利さが求められるように なったのです。さらに、それによって刀剣造りの技術が向上し、戦闘の経験をふまえた創意工 夫の積み重ねによって太刀(日本刀)が生み出されたのです。
太刀の流行した時代をざっと眺めてみましょう。平安時代末期の太刀の特色は、一般的に刀 身の幅が狭く、刀身の形状は手元に比べ先のほうでぐっと細くなり、先端は小切っ先になって います。全体としての反りは深めですが、反りのつけ方が極端に把に近い部分で大きく反ら し、その先の身はほぼまっすぐです。この時代の主な刀工は、京都や奈良周辺と刀剣用の良質 な砂鉄の産出地である伯耆国(島根県)とそれに隣接する備前(岡山県)の一帯でした。ま た、この時代に刀工を保護したことで知られるのは、奈良や比叡山などの南都北嶺の僧兵で す。
鎌倉時代(1185〜1333年)は日本刀の黄金時代といわれる時代でした。源頼朝によ る武家政治体制が確立し、武術が武士のたしなみであるという社会的価値観の成立を背景に、 全国各地に数多くの刀工を生み出し、後世に名刀と伝わる傑作も多くつくられました。その中 の1人に相州正宗がいます。鎌倉初期の太刀の姿は前時代の継続ですが、中期になるとやや変 化して刀身の幅はぐっと広くなります。元と先の幅の差も少なくなり先反りが加わり、大切っ 先になります。先に鎌倉末期になるほど身幅は広くなります。 なお、この時期に作刀の隆盛に刺激を与えた出来事として、後鳥羽上皇(1180〜123 9)の御番鍛治があります。上皇は山城国(京都)の栗田口、備前国、備中国から13人の刀 工を御所に呼び寄せて、月番によって作刀させることによって大いに奨励したのです。後期に なると元冦による非常事態の緊張が武器の充実に拍車をかけました。鎌倉時代に一般に使われ た太刀には、その外装から黒漆(こくしつ)太刀、黒漆白金物太刀、葦(革)包み黒漆太刀を 呼ばれるものなどがあります。
南北朝時代(1336〜1392)には、豪壮でしかも実用本位の太刀が流行し、その特徴 は前時代よりもいよいよ刀身の幅が広くなっていることで重ね(刃の厚さ)は薄め、先端は大 切っ先となります。特にこの時代には鎌倉時代末期頃から使われはじめた、刀身が約85cm という長大な野太刀(のだち)が盛んに使われ、室町時代(1392〜1573)にはやや下 火になりますが、桃山時代にはまた流行します。野太刀というのは外装の立派な上層階級の用 いる太刀に対して、一般の兵士が戦場で用いた質素で実用的な外装の太刀のことです。 当時の名工としては、越中国の義弘、則重、山城国の長谷部国重、来国次、美濃国の兼氏、 石見国の直綱、筑前国の左など正宗の十高弟と言われる刀工たちがいました。 14世紀末に南北朝が統一されて室町時代は一応平安でしたが、やがて中期には応仁の乱 (1467〜77)が全国に波及して地方の大名間の争いが激化し、以後100年間戦国の時 代が続きます。その戦乱によって多数の刀剣が必要になり、大量生産の数打物といわれる量産 品がるくられるようになります。そのためこの時代は、刀剣の歴史の中でいわば質的に低迷の 時代とされています。ただ、この量産の太刀が幕府の制作によって中国に輸出され、明末から 清代に渡って使われたことは特筆されます。やがて室町中期になると太刀に代わって打刀の様 式が登場し、太刀の時代は終息します。
武道における剣法が成立したのは安土桃山時代(1573〜1600)のことですが、それ 以前の時代にも刀剣の操作技術は、ある程度発達していました。「平家物語」などの軍記もの や古記録の中に、戦場で活躍する武器としてしばしば登場するのが長大な野太刀です。その用 法は、だいたいが剛の者が力にまかせて振りまわすといったものでした。それが、戦場の経験 を積むにしたがって効果的な扱い方が定着していき、鎌倉時代の文献には、大向(おおむこ う)、小額、左右の小手、幌突き、高股、胴、骨、大袈裟、小袈裟、車切り、唐竹割、といっ た技法の表現も登場します。いわゆる兵法として体系化されたものではありませんが、その 個々たる技の中には、後世の剣術の技法として取り入れられているものがあります。
3.主な太刀
★毛抜形太刀(けぬきがたたち)
1.形状と用法
刀身と把が一体の共鉄造りで、把の中心線に沿って細長い透し彫りが入っているところが 外見的な特色。その形状が古代の毛抜きに似ていることから、後世にその名が付けられたので す。細身で把元の大きな反りをもつ刀身は平造で、全長が90cmくらいのものが一般的で す。
古い文献には「野剣」(のだち)と記されており、平安時代中期から末期にかけて公家が主 に戦場用に用いました。把の握りが外側に反った形は、騎乗における斬撃に適したものですか ら、主に騎馬による戦闘の時などに腰に佩用したものと思われます。
2.歴史と詳細
毛抜形太刀を太刀の把元に反りをつける形態は、奈良時代から関東以北に流行していた蕨手 刀の影響を受けたものと考えられています。つまり、彎刀の形式は初めて地方で発生し、やが て中央へ伝わって毛抜形太刀へと発展したというわけです。しかし、この段階では「鎬造で茎 方式、彎刀」という完成された日本刀の様式に比べ、ほぼ直刀の平造、共鉄形式ということ で、鍛造技術としては水準が一段低いものです。それがやがて、茎が細くなって把を取りつけ けるようになり、刀身も鎬造りの彎刀となるなど、後の日本刀の特徴を整えていくわけです。 そいっても、これはあくまでも推測なのですが、とにかく、そうした理由で毛抜形太刀は、日 本刀が完成する前段階の形式ではないかと推定されているわけです。
この毛抜形太刀を所有していた人物として有名なのは、関東において朝廷に反旗をひるがえ した平将門(将門の乱=935〜940)を、朝廷の命によって追討した藤原秀郷です。別名 「俵の藤太」ともいいますが、この名で登場する有名な伝説に、琵琶湖の龍女の願いによって 三上山に住むむかでを退治したという話があります。その秀郷のものと伝わる三重県・伊勢神 宮微古館蔵の太刀は、全長が96.3cmというものです。また、平安時代に中央政権で権勢 をふるった藤原一門の氏神である、奈良の春日大社にもこの太刀が宝物として収蔵されていま す。
3.刀剣の長さと反り
刀剣の長さは棟区(むねまち)から鋒(切っ先き)までの距離をいいます。また、刀の反り 具合というときには、棟区から峰を結ぶ直線と刀身の棟との距離が最も長い部分を基準にして みます。反り具合が全体に平均していて、最も距離のある部分が中央にあるものを京反り(華 表反り=とりいぞり)、棟区に近い部分で極端に反っているものを腰反りと呼びます。
□小烏丸太刀(こがらすまるのたち)
平家に代々伝えられていた名剣で、江戸時代の刀剣書に最も古い日本刀の刀工の一人として あげられている天国(あまくに)の作と伝わるものです。形式は鋒両刃造(きっさきもろはづ くり)ですが、両刃の部分が半分以上を占めているという異質な形状をしています。茎の部分 に強く反りがつけられていて、毛抜型太刀と共通する直刀から彎刀への中間様式を示してお り、制作時期も平安初期とみられます。 小烏丸の由来は、伊勢神宮の御使姫である烏が桓武天皇のもとにこの太刀を持って来たとい う伝説によるものです。平貞盛が藤原純友討伐(純友の乱=939)の時に朝廷から賜り、以 来、平家の宝剣として伝わりました。その後、宗氏(対馬の藩主)に伝わり、明治天皇に献上 されたという経緯があります。 なお、刀剣の造込みの形式に小烏造と呼ばれるものがありますが、要するにこの太刀の製法 のことです。正倉院御物として収蔵されているものは、刀身の長さ34.5cmから10.5 cmの間で、そのうち最も多いのは60〜70cmくらいです。反りは少なく、最大で1cm 程度です。
天魁星
(LV1うに談:すごい。すごすぎて声がでない。しかもこれをメールフォームに直接 打ち込まれたらしい。このアバウトな(日本語文献ほとんどないんだもん^^;)武器ページ中、 もっとも高度な内容であります。 ありがとうございました。これを書かれた天魁星さんとは?では 幻夢に読みにいきましょう。)
☆日本の弓☆
この記事は、洋弓のページに統合しました。→こちら
☆日本の「棒」
すみません、順番がかなりばらけていますが、近いうちにまとめますので、ちょっと おまちください。
この記事は、幻夢の天魁星さんが書かれたものです。
形状と用法
ここでいう棒とは堅い木を丸く削ったもののことで、鉄板や筋金など他の物質を加えて強化 処置を施していないものをいいます。
棒の素材は一般に樫(かし)の木が主に用いられますが、それ以外にも杉、柘植(つげ)、 櫟(くぬぎ 別称「一位」ともいう)などが用いられました。これらを丸い棒のまま使った り、六角形、八角形に削って使ったわけですが、その長さは色々ありまして、短いものは約3 0cm(1尺)ほど、長いものは300cm(1丈)を超えるものも用いられたりしていま す。江戸時代には棒術が盛んに行なわれていましたが、そうした流派の一つである柳生心陰流 の伝える棒の長さの基準は、次のようなものです。
1.手切棒(20cm弱) 中指の先から手首までくらいの長さ
2.肘切棒(40cm) 中指の先から肘までの長さ
3.腰切棒(90cm) 地面から腰までの長さ
4.乳切棒(120cm) 地面から乳首までの長さ
5.耳切棒(160cm) 耳の高さまであるもの
6.六尺棒(180cm) 耳切棒より上のサイズ
なお、戦国時代の軍記物では「北条五代記」に剛の者が1丈2尺(360cm)の棒をふる ったという記述もあります。
以上のサイズのうちで約90cm(3尺)までの棒を総称して「半棒」と呼びますが、機能 性、扱いやすさという点では棒術や捕物具などに一般的によくつかわれたのが乳切棒と六尺棒 です。太さはだいたい直径3.5cm前後です。
棒を使うときには、短い棒は片手で持ち、それ以上の長さのものは両手で持って、攻撃にも 防御にも使います。その要領は同じ長棒状の柄をもつ槍や薙刀に通じるといわれます。乳切棒 や六尺棒などの基本的な用法としては、相手の太刀を払ったり巻き落としたりして突き倒す、 あるいは太刀を払って小手を打ち、ひるんだところを突き倒すといった具合。もちろん戦国時 代の鎧武者は防備も固いわけですから、鎧の継ぎ目や無防備な部分、つまり喉、顔面、脇の 下、脛(すね)、金的などの急所を狙って突きます。現代の警官の警棒のような短い棒は振り かぶって殴打したり振り回したりしますが、長い棒は横に振り回せば隙ができ、そこを敵に襲 われてしまいます。ですから、攻撃するときはもっぱら突くことが主になるわけです。その効 果は一撃必殺とはいきませんが、喉を突かれれば窒息しますし、金的を突かれれば失神するこ ともあります。短い棒で殴っても脳震盪を起こすくらいの威力はあります。
棒は叩いたり振り回したりするだけでも効果がありますから、武術の心得のない者でも簡単 に武器として使えるという大きな利点があります。さらに、その素材はどこでも手軽に調達で きます。特に日本では近くの裏山や行けば、すぐに手に入るようなものですから、そういう点 でも非常に便利な武器といえるわけです。とにかく、棒は特殊な強化処置を加えない単純なも のですが、丈夫で折れにくく、攻撃にも防御にも非常に有効な武器です。
なお、棒には別名「槍折」の名もあります。これは戦場で槍の穂先を打ち折られながら、そ のまま残った柄で戦ったことからきたもので、棒の武器としての簡便性を象徴するものといえ ます。
歴史と詳細
棍棒という言葉がありますが、これは棍と棒を総称したものです。中国で「棍」というのは ここでいう棒にあたり、何の加工も強化処置も施されてない棒です。それに対して「棒」は木 に鉄を巻きつけたり、先のほうを太くして重心を前に移すことによって打撃力を高めるなど、 強化処置を施したいわゆる強化棍棒のことをいいます。我が国では金砕棒(かなさいぼう)が これに近いものです。
もう一つ棒と同様な表現に「杖」(じょう)という言葉があります。基本的には「細長い 棒」のことですから、ここでいうところの棒の概念に含まれるといってよいでしょう。古くは 寸法を表わす言葉で1丈(約300cm)の長さをいいました。ただし、「日本書紀」「古事 記」などに使われる1丈は、現在の寸法よりも短く、実際は約227cm(7尺5寸)です。 近世になると六尺棒が最も使い勝手の良い長さとされて棒の定式になりますが、それに対して 7尺5寸の長さの棒を杖を称するようになったと考えられています。ですから杖術で使われる 棒もこの長さが基本となっているといえるわけですが、実際には流派によって約127cm (4尺2寸1分)というものもあれば約166cm(5尺5寸)のものもあります。要するに 流派によってそれぞれ操作しやすい長さが工夫され、それを杖と呼んでいるわけです。
なお、杖と呼ばれるおのには鉄製の吾杖、切籠杖(きりこじょう)がありますが、これは阿 梨棒(ありぼう)といって長さ100〜130cmの鉄製で、先細りの鉄鞭状の形状をしたも のです。
棒は人類が手にした最も古い武器です。我が国で棒が兵器として盛んに使われたことが記録 としてみられるのは、平安時代末期(1156〜1184)の頃からです。「源平盛衰記」の 中にも、弓を持たない者が4、5人ないしは7〜10人で徒党を組み、おのおの好みの杖( 棒)を持って戦場に出たことが記されています。南北朝時代(1336〜1392)になる と、棒や戦場における強力な武器としていよいよ盛んに使われるようになります。この時代、 先頭様式が従来の騎馬戦から徒歩集団戦に変化し、甲冑も軽く動きやすいものが主流となりま す。簡便さという利点の一方で、逆に打撃に対する防護効果は減少します。そこで打撃武器と しての棒の効果も高まったのです。
棒術の発展と流派
多くの戦乱を経験して棒の操作技法にも洗練され、棒術は総合武術の一つとして江戸時代に 大いに発展しました。
棒術は刀剣などの技法と並んで、我が国でも古くから行われた武術で、「日本書記」にもす でに棒の技法に関する記述があります。棒の操作技術の進歩がいちじるしかったのは、激しい 戦乱が続いた南北朝時代です。この時代の戦闘は、力にまかせて振り回し、当たるを幸い相手 を叩き、損傷を与えるというものでした。しかし、180cm前後の重い樫の棒を長時間振り 回すのは、いかに剛の者でもスタミナが消耗します。そこで棒も長短さまざまなものが工夫さ れ、それにつれてより効果的な操作技術の研究がなされたのです。やがて、室町時代(139 2〜1573)になって武術の流派が発生すると、その中の一つとして棒術も確立されていき ます。こうして江戸時代には大いに隆盛して多くの流派が生まれるわけですが、その技法が 「打つ」「突く」「払う」といった要素を基本に構成されており、戦場における乱戦用という よりも個人の格闘の技術でした。
主な棒
○金砕棒(かなさいぼう)
□形状と用法
金砕棒は棒の攻撃力を高めるために加工されたり、他の物質を加えて強化処置を施したもの です。
一般に金砕棒と呼ばれるものには、その強化処置の方法、素材の違いによって3種類に分け ることができます。一つは、堅い木の棒を六角か八角に削り、角を立てることによって打撃面 の衝撃度を高め、さらに手元を細く、先に向かって徐々に太く加工したものです。棒の先の方 に重心を移すことで、力学的に打撃力のパワーアップを工夫したわけです。
棒の長さに長短は ありますが普通212cm(7尺)前後で、最も長いものは約360cm(1丈2尺)という 長大なものもありました。手元の部分は50〜60cmを持ちやすいように丸く削ってあり、 太さはだいたい3.5〜4cmくらい、先端の太さは7cm前後。重さは3〜5kgの範囲で す。素材は樫や櫟(いちい)、柘植(つげ)などの固い材質のものを用います。
←鉄鋲をうったタイプ。資料提供は天魁星さんです。 マウス描きの、このひどい左右非対称の絵はLV1うにです。 すみません。
もう一つは六角形か八角形に削った木の棒に金属を加えて強化処理をしたいわゆる合成棒で す。その手法にもいくつかありまして、棒の打撃部分を鉄板で包んだもの、鉄の筋金を打ちつ けたもの、さらに殺傷力を高めるために表面に鉄鋲を打ったもの、といった形で強化されてい ます。棒の形状は前者とほとんど同じですが、鉄が加わった分重量も増してだいたい5、6k gです。
棒に鉄が加えられるようになると、当然、木に鉄を張りつける手間を省いて鉄だけでつくっ てしまおうという発想も生まれます。そこで南北朝時代(1336〜92)末期頃に登場した のが鉄製の金砕棒です。すべて鉄ですから寸法はやや短くなって150cmくらい、重量は5 kg前後というものでした。
このように強化され威力を増した金砕棒は、単純にその重量からみましても、体力のない人 間ではとても扱いきれるものではありません。ですからこれを所持するのは、体格も良く力に 自身のある豪勇の者と決まっていました。使う時には両手で持ち、とにかく振り回す、打ち下 ろすといった方法で、敵や厚い扉などの物体を破砕します。当たれば鎧の上からでも骨を打ち 砕きますし、頭部を直撃されれば致命傷になります。特に乱戦の中では十人力といえるほどの 働きをし、太刀や槍といった武器よりも威力を発揮しました。
□歴史と詳細
鎌倉時代には棒が補助兵器として用いられたことは、「源平盛衰記」などで物語られていま すが、この時代には棒に加工を施しただけの金砕棒が用いられていました。「義経記」には、 八角棒、櫟棒、ちぎり(乳棒)木などの名前が登場していますから、平安末期から鎌倉時代初 期には加工された八角棒が出現しています。
加工された棒がされに強化工夫された合成棒へと発展し、南北朝時代頃から流行し始めたの が金砕棒です。「太平記」には棒、柏木棒、樫木棒、金棒、くろがねの棒といった呼び名が登 場し、棒に鉄板を伏せた金砕棒をふるって活躍する豪傑の姿が記述されています。室町時代以 降になると金棒、鉄棒とも呼ばれるようになりますが、こうした呼び名は棒を鉄板で包んで強 化したり、材質そのものが鉄に代わったことから呼ばれるようになったものです。
室町時代は、いよいよ激化した戦乱時代でしたので、棒を含めた武器類が急速に発達しまし た。長さも長短各種のものが登場し、強化方法も個人の体力、技術、好みによって異なったよ うです。しかし、重量もかなりのものですから、戦闘の集団化、スピード化する中で豪傑の活 躍する機会は少なくなり、金砕棒はだんだん姿を消していきました。
by 天魁星

 TOP
TOP